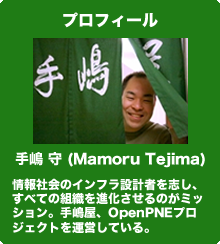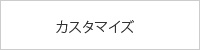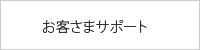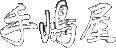社長BLOG
【つぶやき】gitで進化、OpenPNEプロジェクト。
- 2009-10-05 (月)
- 社長BLOG
OpenPNEプロジェクトのソースコード管理をgitへ移行した。これで誰でも気軽に開発に参加できるようになった。コミット権必要なし!レポジトリを汚す心配も無し。forkも自由にできる。
(pne.jpから)
渋谷タワーレコードで、加藤登紀子さんとSNS付きCDの記者発表
- 2009-09-29 (火)
- 社長BLOG
9月28日加藤登紀子さんと記者発表をした。
芸能系の記者発表は生まれて初めてで、場所も渋谷のタワーレコードのステージと、なれない場所、アウェーな感じがしてとても緊張した。渋谷のタワレコって言ったら、普段は客としてCDを探しに行くところではないか。
取材に来てくれたIT系の記者さんも同じ様子で、オフィスの会議室で行われるこれまでの記者発表と違って、渋谷タワレコの地下、ライブステージという空間は異質なようだった。
そんな空気の中記者発表では、登紀子さんが10月7日にリリースするCD「1968」と同時にスタートする1968プロジェクトのSNSの取り組みについての説明をしてきた。
そのとき発表に使ったスライドはこれ。
当日は、津田さんにtsudaってもらい、ケツダンポトフ(PTFLive)にも中継していただいた。
中継は録画されたものがアップされているので、ケツダンポトフのリンクから閲覧できる。津田さんのまとめ方のすばらしさといい、そらのさんの中継セットアップの手際の良さといい、もはや職人芸の域に達している。
忙しいところを調整していただいた。ありがとうございました。
従来の芸能記者、IT記者、津田さん、 そらのさんのようなソーシャル記者?の三つどもえの構図には新しさを感じた。
加藤登紀子さんという大御所のアーティストが、OpenPNEやtwitter iPhoneを駆使して、ファンと直接交流をする。今回この手伝いを手嶋屋ができたことはとてもうれしい。
写真は登紀子さん、iPhoneの操作に頭を抱えるの図。
さすが登紀子さん、今では毎日twitterでつぶやいている(@tokikokato)。教えた甲斐があったというもの。どの書き込みにも感情がこもっている。たまにだが音声もアップされている。すごく素敵だ。
テクノロジーは、これまでの障害や垣根を取り払い、人と人とのつながりを生みだし、組織をひとつにする力があると、改めて感じた記者発表の一日だった。
このSNSを成功させ、アーティストとファンをつなぐSNS、プロジェクトを支援するSNS、商品と連動するSNSなどを提供できるようにしていきたい。
※登紀子さんにiPhoneを教えるのは、たいへん&緊張したよ。
Yahoo! CUが終わる。~ビジネスSNSの勝ちパターンはあるのか?~
- 2009-09-18 (金)
- 社長BLOG
OpenPNEをベースにして作られたビジネスSNS Yahoo! CUが10月で終わるとのこと。
OpenPNEを使ってくれたので、終わってしまうのはとても残念だ。
Yahooでも失敗してしまった、ビジネスSNSを成功させるにはどうしたら良いのだろうか?
CGMサービスの定義は、
「ユーザー同士がコンテンツを作り、楽しむサイトを運営すること」
だと思う。この定義から行くと最強のCGMサービスはオークションだ。
ビジネスSNSをCGM的に解釈すると、こうなる。
「仕事をお願いしたい人と仕事をうけたい人が、お互いに参加する」
「採用したい人と採用されたい人が、お互いに参加する」
「ビジネス知識を披露したい人と身につけたい人が、お互いに参加する」
うまくいっていないビジネスSNSは、このバランスが悪いのだろう。
規模が小さくても良いので、採算に乗せながらこのバランスを維持できるサイトを作り出すことを考えたい。
【つぶやき】もう一つの政治SNS(FreeJapan)
- 2009-09-17 (木)
- 社長BLOG
こちらもOpenPNEでできている。 http://sns-freejapan.jp/
(pne.jpから)
【つぶやき】東京ライフSNS復活!
- 2009-09-17 (木)
- 社長BLOG
東京ライフ 電子フォーラムはOpenPNE3で構築されている。今度はうまく運営してね。 http://sns.tokyolife.jp/
(pne.jpから)
【つぶやき】最強の分類方法
- 2009-09-17 (木)
- 社長BLOG
多くの人にとってもっとも有効な分類軸は、「人」と「時間」だ。「超」整理法は「時間」、twitterは「人」と「時間」。
(pne.jpから)
DB定義書を出さない会社は信用できない。
- 2009-09-11 (金)
- 社長BLOG
最近よくあること。
1.他のシステムからOpenPNEに乗り換えたい。
2.データ移行をしたいが、元のベンダーがDB定義書を出さない。利用規約の中で、DBの解析や逆アセンブル禁止とされている。
3.企業が渋っているうちに、ライセンス費用や運用費用がかかり続ける。
ソーシャルデータという、組織の根幹をなすようなデータが、一企業にロックインされているという状況は、どう考えてもおかしい。
データを人質に取るような商売は、お客さまのためにはならない。