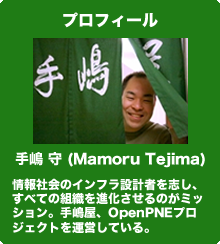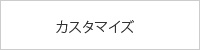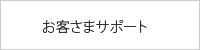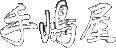社長BLOG
「サマーウォーズ」を観て、OpenPNEを考える。
- 2009-09-11 (金)
- 社長BLOG
「サマーウォーズ」を観てきた。
いわゆるアバターSNSなんだけど、遊びだけでなくビジネスや行政サービスもうけられるOZという空間を舞台にした物語。
仮想空間上で行政サービスがうけられると言う部分は、OpenPNEの構想とも近く、非常にわくわくした。それがアバターでというのがかなり引っかかった。自分の好みとしては、仮想空間についてはもう少しシリアスにしてほしかったというかんじ。
でも、この映画の主題である家族の絆については、ぐっときた。
OZはOpenPNEで実現された!と言われるようになりたい。
【つぶやき】ついぴーね、デザインをすこし改善しました。
- 2009-09-06 (日)
- 社長BLOG
これから機能の作り込み。ちなみにここまででOpenPNE3.1本体はソースコードに一切変更を加えていません。すべてプラグインを編集するだけ。この記述力はすごい!
#twipne みく
(pne.jpから)
OpenPNE投稿APIについて
- 2009-09-06 (日)
- 社長BLOG
OpenPNE2をついぴーね対応サイトにするためには、投稿APIを追加する必要があります。
手順
0.OpenPNEのバージョンを確認する
2.10 2.12 2.14に対応しています。
1.APIファイルをダウンロードする
ここからファイルをダウンロードします。
2.ファイルの設置
SA.php は /webapp/lib/に設置
xmlrpc以下のファイルは /webapp/modules/api/lib/xmlrpc に設置
3.設定ファイルの変更
config.php
// API通信使用設定
define(‘OPENPNE_USE_API’, true);
に変更
4.c_apiテーブルの更新
insert into c_api (name) values (‘sa_000_auth’);
insert into c_api (name) values (‘sa_010_h_add_diary’);
insert into c_api (name) values (‘sa_110_c_add_topic’);
insert into c_api (name) values (‘sa_112_c_edit_topic’);
insert into c_api (name) values (‘sa_120_c_add_event’);
insert into c_api (name) values (‘sa_122_c_get_event_member_list’);
insert into c_api (name) values (‘sa_123_c_edit_event’);
insert into c_api (name) values (‘sa_130_c_add_topic_comment’);
insert into c_api (name) values (‘sa_131_c_get_topic_detail’);
insert into c_api (name) values (‘sa_132_c_get_topic_detail_2’);
5.管理画面からAPI許可IPアドレスを設定
pne.jpサーバからのAPIアクセスを許可する
2009/10/04時点でのIPは(75.101.230.67)
「SNS設定」=>「API設定」から追加したAPIを利用可能にします。
【つぶやき】本日のゲリラブレストは盛況だったなぁ。
- 2009-09-05 (土)
- 社長BLOG
生まれた言葉は「ランチアライアンス」手嶋屋とのランチアライアンス提携企業募集中です。アライアンスパートナーにはもれなく手嶋屋特製ランチランダマイザーをプレゼントします。
みく
(pne.jpから)
湯川さん良い事書いた!「すべてのメディアはソーシャルに向かう」
- 2009-09-04 (金)
- 社長BLOG
湯川さんがメディアはソーシャルメディアに必然的に向かうと言う記事を書いた。
ソーシャル100%の自分にとっては、メディアがソーシャルに来てくれると商売的にも、個人的にもとてもうれしい。
すべてのメディアはソーシャルに向かう
大変革期を迎えたマスメディア企業への提言
「すべてがSになる。」
そういえばこの言葉をOpenPNEオフィシャルガイドブックで書いた。SはソーシャルのS。
OpenPNEオフィシャルガイドブックはこれ。絶賛発売中。
湯川さんは、ソーシャルになるところまでは見通したのだが、ソーシャルになった後、どのようにして儲けたら良いかについての答えはまだでてないのではないか。
この答えを出すのが実業家の仕事だ。
・ニッチコンテンツ課金モデル
・会員クラブモデル
・ソーシャルおひねり&広告モデル
今のところ3本考えた。もっとひねり出そう。
新聞社の新ビジネスモデル【ソーシャル編】
- 2009-09-04 (金)
- 社長BLOG
ソーシャル研究家としては、新聞社がトライしようとしているビジネスモデルだけを論じても始まらない。
ソーシャルを活かした、新しいビジネスモデルをひねり出してみた。
ビジネスモデル1「会員クラブモデル」
これは日経新聞がやるとはまるビジネスモデルだ。前の記事で書いたが、日経新聞を読む価値の半分は「経済人はみんな読んでいる」というコミュニティ要素にあると思っている。
であるならば、このことを自覚しコミュニティを維持発展させることにあてればいいだろう。
製造業限定交流会、上場企業限定交流会、経理限定交流会、人事限定交流会など、タテ、ヨコ、ナナメに切った、交流会、勉強会、セミナーを開きまくるのだ。
上質なマッチングと、読者同士のコミュニケーションを売り物にしよう。
新聞はこのコミュニティに参加するためのチケットであり、読者が交流するためのお題になるのだ。
ビジネスモデル2「ソーシャルおひねり&C2C広告モデル」
2番目はかなり飛んでいる。まだ思考実験を始めたばかり。
ビジュアル的にはこんな感じ。
記事は一般に対して無料配信する。新聞コミュニティのメンバーは、共感した記事や、一言モノ申したい記事。または、自社のPRにつながりそうな記事に対しておひねりをとばすことができる。
記事と同一画面内に、写真とID名、おひねり金額を表示させることができるのだ。
リンクも貼られているので、自分のプロフィールページに誘導することもできる。
「2010年オゾン層が危機的な薄さに」
と言う記事に対しては、コパトーンあたりが、急いでおひねりをとばせば、有利な位置に露出することができる。
企業と個人ではおひねりの額の桁が違ってくるだろうから、うまく分類してあげれば良いと思う。
個人の場合でも価値があると思っていて、
「さすがです、社長!あの記事におひねりとばしてましたね!」
という、コミュニケーションのきっかけになればいいなと思う。
新聞社の有料課金モデルは成立するのか?
- 2009-09-04 (金)
- 社長BLOG
米国の新聞社が有料課金モデルを始めようとしている。
うまくいくのだろうか?
有料課金というと、みんなが思いつくのはコンテンツ課金モデルだ。
月会費制にせよ、1記事5円のマイクロ課金制にせよ、どちらも共通して
「価値のある記事は、お金を払った人にだけ読ませてあげる」
と言うビジネスモデルだ。
ここで、新聞のコンテンツ課金分野において、読者が何を価値としてお金を払うか考えてみると、
1.情報の質が良い
他で手に入らない、自分にとって価値ある情報が提供されている
おもしろい、ためになる、気づきがあるなど
2.情報をタイミング良く、効率よく吸収できる
配達されるので朝パジャマを着たままで読める
面が大きいので、一気に情報を読める
紙なので、食卓、キッチン、洗面などで気軽に読める
こんなかんじか。
コンテンツとしての新聞の価値は、日本では特に、紙が現場に届くと言う価値は相当高そうな気がするなぁと言う印象。
自分はコンテンツ課金における、新ビジネスモデルが成功するかどうかは、1.2.のふたつの要素にかかっていると思う。
有料にすることで、1.2.の両方を向上させることができればいいが、どうも2.を損なってしまいそうな気がしている。
たとえば、家のブラウザでは課金登録してあるから、すんなり読めたけど、会社からだとIDとパスワードの入力を求められて、コンテンツを読むのに20秒余計にかかった。
なんて事があったら、完璧にアウトだ。もう立ち直れない。
でも、なんとなくこうなりそうなんだよね。こういう対策考えているのだろうか?
ニッチなコンテンツは課金する。ほかで情報を得るのはもっと大変だから、少々不便な方法でもOK。
一般ニュースは制限しないでまきえさにする。どこよりも超便利なサイトにする。
が勝ちパターンだろう。
※実は、ソーシャル研究家としては、第三の切り口があり実はこれがキモになるんじゃないかと思っている。
既存メディアがtwitterを活用する勝ちパターンはあるか?
- 2009-09-04 (金)
- 社長BLOG
twitterがバリバリ来ている。既存メディアも早く食いついた。
個人的には産経新聞の「下野なう」は高く評価しているのだが、一部のtwitterコミュニティは許さなかったようだ。
ここは踏ん張ってほしかった。残念でならない。
産経新聞だけでなく既存メディアは、twitterに参入してどうすれば自メディアの活性化につながるかを模索している。
果たして、既存メディアがtwitterを活用する勝ちパターンはあるのだろうか?
自分は、既存メディアにおけるtwitterの一番の利用価値は
「既存メディアが自分の高いランクを捨てて、ユーザーと同じ目線になる」
ここにある。
「わ!コメントしたら、返事が返って来ちゃった!」
「なんだ、お高くとまっていたと思っていたけど、自分と同じ目線で話ができる相手なんだ」
と言う印象を与えるのに、twitterは一番向いていると思う。
この印象を与えて、どう収益につなげるか?がキモなんだけれど、そこはメディアの性質によってかわるので、それぞれ考える必要がある。
さてここで、新聞社のtwitterアカウントの写真を見比べてみよう。
このアカウント写真で、どの写真が一番効果的か?
「既存メディアが自分の高いランクを捨てて、ユーザーと同じ目線になる」
このテーマに沿って、考えた方が良い。
あ、こうは言っているけど、誤解を与えたくないので補足を。自分は別に読者にこびをうれと言っているわけではない。「なんならプロとして読者と一対一でも議論してやるぞ」ぐらいの意気込みでぶつかってくれても良い。
読者と同じ目線でものを見て、同じ土俵で話をしてくれさえすれば良いのだ。
そうそう、このブログ書くに当たって調べたけど、
こんなの良いよね。
SNS繁盛概念図「ソーシャルメディア」
- 2009-09-03 (木)
- 社長BLOG
「テクノロジーにより、ルールが変わった」既存メディアに対する問題意識
- 2009-09-02 (水)
- 社長BLOG
メディアに対する問題意識。
・テクノロジーの進歩によって、既存メディアの優位性が失われた
・スピード、配信範囲などの能力において、ある面では小学生にも負けるようになった
・メディア枠の独占ができなくなった
・読者ニーズの多様化に対応できなくなった
・広告の費用対効果が悪いことがばれてしまった
・メディアを作るコストがめちゃくちゃに安くなった
・生きるために、どうしても必要な情報が少なくなってきた
こうした環境やルールの変化に、既存メディアが対応できていない。
新聞社向けに話そうと思う内容はこんなところ。
・マスメディア、インタラクティブメディア、ソーシャルメディアの違いを理解しよう
・新しい競争ルール(スピード、非独占、PV/UU)を理解しよう
・意識されないメディアの価値(「信頼」「つどい」「思考停止願望」)を理解しよう
・新聞社が取るべき戦略(コスト削減、能力向上)を考えよう
・アイデア(新聞から「真聞」「深聞」へ)
OpenPNEを使ってこれらの課題をどう乗り越えるか?
一緒に考えましょう。