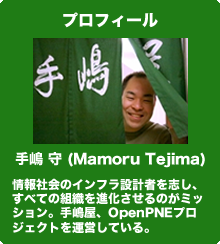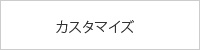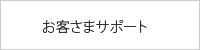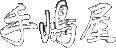社長BLOG
ついぴーね対応サイト
- 2009-08-12 (水)
- 社長BLOG
現在対応しているサイトと投稿用のキーワードは以下のとおり。
随時更新していきます。
登録済みのメジャーサイト
・Twitter ※20090810対応
キーワード: twitter つい 対
・Remember The Milk ※20090812対応
キーワード: みるく
設定可能なサイト
WEBサービス立ち上げの最適な体制は1人
- 2009-08-12 (水)
- 社長BLOG
※スダックス ビジネスレター経由
WEBサービス立ち上げに最適な体制は1人
やっぱりそうなんだよなと思った。前々から思っていたけど、確信が持てなかった。ヨセミテblogを読んで改めて納得した。
※ヨセミテさん、須田さんありがとう
手嶋屋で開催するハッカソンのテーマを考えていたが、これに決めた。
「ハッカソン:1人でサービスを立ち上げる会」
にする。参加したい人いるかな?
オンライフのサービス終了とヨセミテの体制変更について « ヨセミテBlog
結論としては、Web上でサービスを立ち上げるときに最適な体制は * プログラミングができる人であれば1人(プロデューサー兼エンジニア) * プログラミングができない人であれば2人(プロデューサーとエンジニア)
.
ついぴーねの使い方
- 2009-08-12 (水)
- 社長BLOG
サイトのURLはhttp://pne.jp
この図のように、件名の一行目に投稿したいサイトのニックネーム、二行目以降に内容を書くことで、簡単にサイトを選んで投稿できる。
キーワード
つ twitter
り RememberTheMilk
ソーシャルエージェント開発予告「掃除ランダマイザー」
- 2009-08-11 (火)
- 社長BLOG
手嶋屋で大ヒット中のランチランダマイザーに続いてのソーシャルエージェント第二弾は
「掃除ランダマイザー」
掃除当番をランダムで決めてくれるエージェントプログラムだ。
散らかしたまま帰宅したスタッフ用のペナルティ機能も搭載予定。
※うまくいったらOpenPNE Officeにオプション提供します。
iPhoneで新聞は生き残れるか?【つぶやきまとめ】
- 2009-08-11 (火)
- 社長BLOG
佐々木俊尚さんのつぶやき読んで思いついたこと。
iPhone版雑誌オンラインアプリの紹介 – 雑誌そのまま、ネットで読める – 雑誌オンライン.COM http://www.zasshi-online.co… 雑誌の版面そのままではやっぱりモバイルでは読みにくいことがわかる。産経のiPhoneアプリと同じ。
iPhoneで産経新聞を読むのは確かに大変ですが、進化の余地があると思いました。ごはん食べながら読むのに使えるぐらいまで改善すれば、少なくとも私は有料で定期購読します。今後新聞紙面とiPhone両方で耐えられる紙面レイアウトは考えた方が良いのではないかな。
たとえば、産経iPhoneアプリは倍率を3倍にすれば何とか読めるレベルになります。新聞そのもののレイアウトを1ページ9分割にすれば良いと言うこと。今の段組はiPhoneでは見にくいです。雑誌なら4分割レイアウトにするとか。そのぐらいの覚悟があれば生き残れると思います。
新聞は長い時間をかけて、サイズ、紙質など現在の形に最適化してきたはずです。最近でも、年寄り仕様に文字を大きくしたり。そうした対応をしてきたわけですから、ニューメディアに対しても保守的な最適化をしていくべきだと思います。21世紀のハラキリレイアウトを目指せ!かな
ハラキリを知らない人のために。
「知っておきたい紙面構成のタブー」http://bit.ly/JVroW
eラーニングから、eクラス、eキャンパスへ
- 2009-08-11 (火)
- 社長BLOG
eラーニングワールドが終わって一番感じるのは、eラーニングの世界にSNSは必要なんだなということ。
eラーニングは、空いている時間に一人一人がただ問題を解いていくだけでなく、クラス、スクールという単位で、参加メンバー、期間をそろえて仮想的なクラスをつくろうと言う段階にきた。
ここが今回のeラーニングワールドのメインテーマになんだなと思った。
ここにOpenPNEが参入して提案したいのは「キャンパスライフ自体のバーチャル化」だ。
自分の経験でもそうだが、大学の価値の半分以上は、キャンパスライフにあるのではないか?
「学科の仲間」「サークルの先輩後輩」「ゼミや研究室のメンバー」「大学近くのアルバイト」
同じ境遇の仲間達との出会いや、交流、学生生活自体が、社会性を身につけたり、人脈や見聞を広げる大事な要素だった。
OpenPNEはこうした組織のコミュニケーションを、クラスやカリィキュラムに縛られずに、自由に、有機的につなぐことができる。
OpenPNEでeラーニングを、eキャンパスに変えることができれば、今回の取り組みは大成功だとおもう。
※デジタルナレッジさん、いっしょに頑張りましょう!
SNS構築に関しては、手嶋屋に直接相談していただきたい。
- 2009-08-07 (金)
- 社長BLOG
企画段階は終わり、開発段階の時点で手嶋屋に回ってくる案件に苦労することがある。
開発段階で回ってくると、コミュニティ設計、機能設計がまずく、これからではどうにも挽回できないと言う状況に陥りやすい。
手嶋屋にはこだわりがある。OpenPNEを使ってもらう以上、運営に成功してもらいたいと言う気持ちがどこよりも強い。
成功するSNSを作るために努力をしている手嶋屋の開発者にとっては、こうした開発は不幸であり、そもそも依頼主やエンドユーザに一番迷惑がかかる。
ということで、ことSNSの構築に関しては、どんな相談からでも直接弊社にまずご連絡をいただきたい。
お問い合わせはこちらから。
※難易度が高いものは手嶋あての直接連絡でも対応します。 メールアドレスは tejima@手嶋屋ドットコム まで。
なぜ在学生と卒業生はSNSを分けなければならないか?
- 2009-08-07 (金)
- 社長BLOG
答えは簡単。組織が違うから。
SNS設計の最初にして最大の難関は、
「どんな組織に対してSNSを作るか?」
「SNSに誰を入れて、誰を入れないか?」
の見極めだ。運営者としては、SNSのユーザー数は多い方がいいだろうから、テーマに合うかぎり出来るだけ大きなユーザーベースを対象にしてSNSを運営しようと思う。
しかし、自分の運営経験上、これははっきり間違いだと言える。
考えるべきは、どれだけ多くのユーザーを抱え込めるかではない。
「参加者がこのSNSに参加しないと話せない話題があるか?」
「参加者がこのSNSに参加しないと得られない人間関係があるか?」
「参加者がこのSNSに参加しないと得られない所属意識はあるか?」
このように運営者の意識を一旦忘れ、ユーザー一人一人の参加モチベーションを考えた上で、SNSの組織設計を考える必要がある。
ということで、在学生と卒業生の話に戻る。
在学生同士では、主に現在のキャンパスライフについての話題が多くなるだろう。
「歴史Iは代返が聞かない」「確率の試験対策プリントが出回り始めた」「今日のサークルは18:00~」と言う感じ。おそらく毎日ログインして使うツールになる。この輪の中にOBが入ってきてもコミュニケーションのスピードが全く合わない。技術的にも、大学が在学生向けにSNSを提供するのであれば学籍番号とひもづけるのが一番素直である。卒業生に学籍番号を振ることはまれなので、これも障害になる。
卒業生同士の交流は、在学生同士ほど活発でないだろう。年に数回もログインすれば良いのではないか?年に数回しかログインしなかったからと言って、失敗ではない。寄付金依頼付きの同窓会会報誌が送られてきて、読まずにそのまま捨ててしまうよりはよっぽどまし、と言うことだ。
他にも分けなければならない理由は色々あるのだが、それはまた今度。
なぜ大学にOpenPNEが必要なのか?
- 2009-08-05 (水)
- 社長BLOG
従来大学は主に18歳の高校生を対象にして新入生獲得のプロモーション活動を展開してきた。しかしながら、少子化の進行に既存メディア離れが重なり、プロモーション活動は大変厳しい状況になっている。
少なくともこれから20年は高校生が増える気配はない。既存メディア離れの進行も続くから、短期的に高校生へのプロモーションの困難さが解消される事はないだろう。
この厳しい状況の中手嶋屋が提案するのは、OpenPNEを使った
「卒業生を見込み顧客に変えるプロモーション活動」だ。
どこにいるかわからない赤のゾーンの高校生をねらうよりも、大学とつながりの深い青のゾーンの卒業生を相手にしたほうが、ずっと効率が良いのではないか?という単純明快、単細胞な手嶋屋のロジックである。
すでに大学は生涯学習を掲げ、社会人大学院や、オープンカレッジ、eラーニングなどを展開している。受け皿の準備は整いつつあるのだ。後は本気で卒業生に対してアプローチをするだけだ。
では、いったいどのように卒業生にアプローチすればよいのか?
その答えが、卒業生コミュニティすなわち「同窓会」なのだ。
旧来型の単なる同窓会をOpenPNEというインフラ上で展開することで、「卒業生プロモーション活動の拠点」に変えることができる。
キーワードは
「大学3.5年生からのコミュニティ参加」
「生涯メールアドレスの提供」
「研究室の数×4の同窓会を毎年運営」
「社会人大学院へのお試しとしてのeラーニング提供」
詳細は現在開催中のe-Learning WORLDで詳しく説明をしている。このデジタルナレッジブースでご相談いただくか、手嶋屋の問い合わせフォームまで直接ご連絡いただきたい。
購読型のメディアは十分やれる(コストさえ下がれば)
- 2009-08-02 (日)
- 社長BLOG
広告料だけが頼りのネットメディアに対して、新聞と雑誌はエンドユーザーからの購読料も収益源になっている。
最近新聞、雑誌はだめだだめだと言われるが、ネットメディアのビジネスモデルに比べれば、よっぽど健全ではないか。
メディアが持つ各要素を構成するコストを購読料に見合う形で下げることができれば、十分良い商売なはずなのだ。
たとえば新聞業界でざっと考えると
・余計な設備はやめる。(支局、ヘリコプターなんかも持ってるらしい)
・妥当な水準まで給料を下げる。
・輪転機は昼間誰かにレンタル、夕刊刷らなくなるんだし。
・配達所も何かに使えないか?クロネコヤマトと一部シェアするとか。
自分のように10年近くふわふわ、ふらふらしたネットの世界に身を置いていると、既存メディアのどっしりとしたところには、ある種のあこがれを感じる。
このどっしり感を活かしつつ、OpenPNEで改革の手伝いができればうれしい。
※自分の母親は新聞が無いと困るという。自分は読んではいないが、新聞代は払っている(もちろん朝日新聞ね)。家族割りなんてやってくれないだろうか。親子の共通の話題がほしいのだよね。