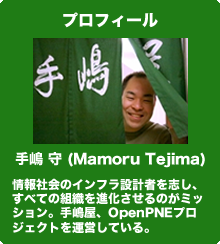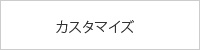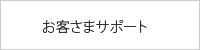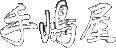社長BLOG
【4/28 19:25~】プライベート勉強交流会 2回目を開催
- 2009-04-17 (金)
- 社長BLOG
ホンネとタテマエが交錯するSNSコミュニケーション。
みんなの前では、話せないことがある。
実は最近、参加者の業種を絞って、プライベート勉強交流会を行っている。
今度の勉強会は、4/28 ゲーム関係者限定で開催する。
※興味がある方は、直接手嶋に連絡してください
【センチメンタル】自動化、効率化を阻む最後の砦
- 2009-04-16 (木)
- 社長BLOG
企業組織にとって、効率は良いにこしたことは無い。
本来、組織運営を成功させたいのなら
何でも自動化して、効率化して、生産性を上げればいいのだ。
それでも、非効率なものを使い続ける理由は
1.ビジネス上の一部の機関(法律、役所、企業、設備)が古い
2.働く人が、新しいものについていけない
3.人間の情緒が、自動化、効率化に拒否反応を示す
こんなところが、ぱっと思いつく。
1.と2.は時代の移り変わりや人の努力で解決ができそうだが、3.の解決がなかなかやっかいだ。
たとえば、ハードカバーの本なんて、その中の情報にとってはいまさら何の役にも立たないのに、未だにたくさん売っている。六法全書だって今時紙で引く人はいない。
※いたらごめんなさい。
テレビのインタビュー時の背景くらいにしか使えないだろう。
でも、そんなセンチメンタルなところが、人の弱さが、自分は好きだし、今後も大切にしていきたい。
センチメンタルを、人の弱さを意識しながら、いかに効率的なサービスを開発するかが、今後のキーになる。
Amazon Kindleなんかが成功するには、センチメンタルな配慮が、実は重要なのかもしれない。
フォントはライセンスフリーに。
- 2009-04-16 (木)
- 社長BLOG
MS OfficeからOpen Officeに移行すると、レイアウトがおかしくなる。
色々原因はあるのだが、MS Officeで使っていたフォントがOpen Officeで使えなくなることが、レイアウト崩れのひとつの要因になっている。
ということで、日本のCTOになったとしたら、
・ライセンスフリーフォントをもっともっと増やす(IPAフォントのような)
・政府の一般的な事務文書はMSゴシックやメイリオではなく、ライセンスフリーフォントの利用を強制させる
・日本国内で出荷されるソフトウエアの標準フォントを、ライセンスフリーフォントに強制させる
もちろんデザインを綺麗に見せる必要がある場面では、商用のフォントを使うべきだし、商用フォントを否定するつもりは全くない。
今回は、「情報を自由に、スムーズに流通させる」という観点で話している。
IPAフォントが2009年4月中旬にもオープンソース・ライセンスへ,改変と再配布が自由に:ITpro
独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)は2009年4月中旬にも,同機構が配布しているIPAフォントを,改変と再配布が自由な新ライセンスで新たに配布する。
.
ビジネスホンを再構築する【OA2.0】
- 2009-04-16 (木)
- 社長BLOG
OA2.0という言葉を作ってみたが、ひとまずこの言葉を
「既存のOA機器やオフィスワークを再構築する試み」
と定義する。
最初に取りかかるのはOA機器の代表選手、ビジネスホンの再構築だ。
手嶋屋は創業してから丸7年の会社だが、未だにビジネスホンを導入していない。
しかも会社を作って2年間は、固定電話すら準備せずに会社用PHSの番号を名刺に書いていた。
創業当時は、手嶋屋はネットベンチャーだし、03番号だから安心なんてどうでも良く、
「電話はつながることが大事」「事務はいないし自分が出る、ならば持ち歩いた方が親切」
と思っていた。
それが今や社員が15人もいる会社になった。取引先も増え、電話で話したいというお客さまも増えてきた。
あらゆる組織にOpenPNEを提供しようとしている企業である以上、いろいろなお客さまのコミュニケーションスタイルに合わせる必要がある。
現在はパナソニックの家庭用電話機2セットで対応しているが、これもそろそろ限界に来ている。
いよいよ我が社にもビジネスホンを導入するタイミングがやってきた。
しかし、いまさらPBX付きの固定電話を入れるのも芸がない。
オフィスの移転もありそうだ。
手嶋屋らしい、OA2.0らしいビジネスホンを導入したい。
・柔軟に組織の拡大や変更に対応できる
・頻繁なオフィスの移転に耐えられる(その都度工事はいやだ)
・当然ながらOA2.0の要となるOpenPNEと連携する
・新しいワークスタイルに合う設計
・コストを従来の半分に
これらの条件を満たせれば上出来だ。いろいろ探してみた結果、ブラステル社のBasixを試してみることになった。
IP電話サービスはたくさんあるのだが、Basixはなんだかマニアックな機能がたくさん付いている。これは開発会社である手嶋屋としてはとても魅力的だ。しかもグローバル企業であるので、OpenPNEの世界展開にも視野が広がる。
問い合わせてみたところ、特別にトライアル利用をさせてくれるとのこと。色々試してみてフィードバックしたい。
セルフSNSなるものが登場した。
- 2009-04-16 (木)
- 社長BLOG
ねとらぼによると、1人遊び専門SNS「セルフSNS」がオープンしたとのこと。
去年のエイプリールフールに「おひとりさまSNS」という企画をやったことがあったが、まさかこのようなコンセプトがまた出てくるとは思わなかった。
この世のあらゆる組織の表現を目指したOpenPNEプロジェクト。
この際”1人”も組織に含めるべきだろうか。
ねとらぼ:1人遊び専門「セルフSNS」 「SNS本来の趣旨を大幅に逸脱」 – ITmedia News
1人遊び専門という変わり種SNS「セルフSNS」が登場した。「参加者同士がコミュニケーションの輪を広げるSNS本来の主旨を大幅に逸脱」し、「自分の中だけの妄想や空想、独り言や妄言、夢や憧れ、1人遊び、個人単位での創作活動などに特化した、斬新なSNS」という。
.
OA2.0 – オフィス(オーガニゼーション)オートメーション 2.0
- 2009-04-13 (月)
- 社長BLOG
OA機器のOAは「オフィスオートメーション」の略で、会社組織が紙と手作業で行っていた業務を電子化し、定型作業を自動化しようというもの。
どうも、自分が物心つくまえからあった言葉らしい。
OA2.0はOpenPNE上で組織のコミュニケーションや業務を行うことで、組織運営を電子化、自動化しようという試み。
OpenPNEは人と組織を表現し、WEB上でその活動を行えるようにするためのソフトウエアである。
OpenPNEで、OAという言葉を再定義したい。
digsbyのFaviconの使い方がカッコいい
- 2009-04-08 (水)
- 社長BLOG
digsbyはいろんなWEBサービスの新着情報をお知らせしてくれる常駐アプリ。
Gmailの新着メールをお知らせしてくれるのだが、Faviconの使い方がカッコいい。送られてきたFromのメールアドレスのドメインからFaviconを取得するのだ。
1.tejima@tejimaya.comからメールが届く
2.http://tejimaya.com/にアクセスしてFaviconを探す
3.見つけてきたFaviconをお知らせ欄で写真のように表示する
よくできてる。
既存メディアがソーシャルメディアを立ち上げるときによくする失敗
- 2009-04-08 (水)
- 社長BLOG
ソーシャルメディア事業者は原則的にコンテンツを作ってはいけない。
でも既存メディアはコンテンツを作って流すことに慣れているので、ついつい自前で(または買ってきて)コンテンツを消費者に提供してしまうのだ。これが既存メディア事業者が引き起こす主な失敗の原因だ。
「一方の消費者が作ったコンテンツをもう一方の消費者が楽しむ」という構図を作ることが、ソーシャルメディア事業者の使命である。
ソーシャルメディア事業者は消費者から上がってくるコンテンツの整理や誘導、インセンティブの提供、たとえば、
コンテンツにランキングをつけたり、ジャンル事に整理分類したり、コンテンツを販売(書籍化など)する際の仲介役を務めたり、ということに専念することが大事である。
マスメディアの3つの力
- 2009-04-08 (水)
- 社長BLOG
1.制作力
コンテンツを作りだす能力。新聞やテレビの記者による取材記事、社説、お天気お姉さんから、局アナまで、メディア事業者から生み出された物をさす。
2.配信力
コンテンツを配信する能力。新聞や折り込みチラシを配布したり、電波に乗せて、映像や音声を多人数に提供すること。
3.信頼
長期間マスメディアを運営してきた信頼。「100年の歴史のある●●新聞に載っていれば、それは事実」という消費者の意識。
これまで独占的、強大な配信能力に支えられているおかげで、マスメディアは発展してきた。
最近、テレビや新聞の元気がなくなってきたのは、配信力が独占的ではなくなり、特に新興メディアに対し相対的に力を失ったことが原因だ。個人でもWEBと検索サイトの組み合わせで、マスメディアと同等以上の強力な配信能力を手に入れることができるようになった。ネットの進化は止まることが無いので、こうして失った配信力の地位はもう取り戻すことができない。
マスメディアは、2.配信力の優位は失われたので、これからは1.制作力ないし3.信頼で頑張っていこうということになる。
3つのメディア
- 2009-04-07 (火)
- 社長BLOG
SNSでソーシャルメディアだ!という話が増えている。
原理原則が好きな自分としては、そもそも論として、ソーシャルメディアにいたるまでのメディアの変遷について、考えてみたい。
1.マスメディア
2.インタラクティブメディア
3.ソーシャルメディア
1.マスメディア
いわゆる新聞、雑誌、ラジオ、テレビなどのメディア。
不特定多数に安価で情報を配信することができる。
メディア事業者=>消費者への単方向通信であることが特徴。
2.インタラクティブメディア
メディア事業者と消費者の双方がコミュニケーションできるメディア。
メディア事業者=>消費者への通信が太く、その逆が細いことが普通。
「テレビにおけるテレゴング」
「ラジオにおけるはがき職人」
「雑誌における読者投稿」
のような位置関係。消費者からの登り通信が増えすぎるとメディア事業者がパンクしてしまうため、あえて細めにしている。
3.ソーシャルメディア
情報発信の主役がメディア事業者ではなく、消費者からの発信になるのがソーシャルメディア。
SNS、pixiv、Youtubeなど一方の消費者が作ったコンテンツを、もう一方の消費者が楽しむというコミュニケーション構造。
メディア事業者は、原則コンテンツはつくらない。
どれがいいか?というのはまた別の話。
※サーバダウンしてからブログが書けなかったのですが、再開します。